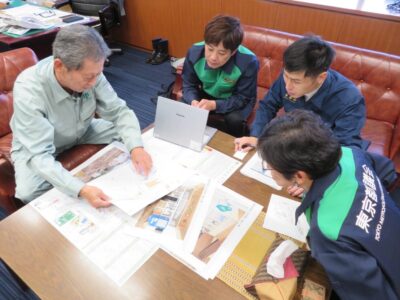「2025年台風22号・23号に対する支援に関する申し入れ(第2次)」について
日本共産党都議団は4日、標記の申し入れを小池百合子都知事あてに行いました。総務局の高田照之総合防災部長、渡邉和成防災管理課長が応対し、「知事にしっかり伝えます」「各局が都立学校や町立小、中学校の復旧、住居の確保、水道の復旧、住民の心のケア、産業支援など多岐にわたり支援を行っており、引き続き支援に取り組みます」と答えました。
(左から)大山とも子、藤田りょうこ、尾崎あや子、清水とし子、斉藤まりこ、(総合防災部長)、田中とも子、原のり子、とや英津子、里吉ゆみ、米倉春奈の各都議
八丈町で被害実態調査を行う(左から2人目から)、原田あきら都議、山添拓参議院議員、田中とも子都議(=10月29日)
東京都知事 小池 百合子 殿
2025年台風22号・23号に対する支援に関する申し入れ(第2次)
2025年11月4日
日本共産党東京都議会議員団
10月に発生した台風22号・23号の八丈町や青ヶ島村の被害について、日本共産党都議団は現地の聞き取り調査を行い、10月15日、知事に対して被災した住民の生活と生業の再建やライフライン復旧を支援するよう申し入れを行いました。都が被災自治体の要望もふまえ行なっている人員派遣や支援物資輸送、予備費活用などは、現地を励ましています。被災地で活動する職員の皆さんに心から敬意を表します。
被災から3週間がたち、島の中では日常生活を取り戻しつつある地域がある一方で、依然として415世帯(10月31日時点)が断水状態にあり、大規模な土砂崩れなどにより、復旧のめどが立たない状況に置かれている地域も残されています。地域の主要な産業である観葉植物やレモンをはじめとした農作物の被害は甚大です。長期間にわたる浜止めで漁に出られない漁業事業者、台風で乾燥機が破壊されたくさや業者、店の大部分を破壊されたラーメン店など、多数の島民が被害をうけ、生業の再建にめどが立っていません。
こうした状況のもとで国が激甚災害指定する見込みを表明したことは重要です。これに伴う自治体連携補助金の使い方の計画は、東京都が策定することになります。都の役割はきわめて重いものがあります。
日本共産党都議団は党国会議員団とともに、10月29日に八丈町に入り、被害実態調査を行いました。その結果をふまえて、島民の生活と生業を一日も早く再建させるための必要な支援を、以下要望します。
- 激甚災害指定にともない行われるかさ上げされた補助を活用し、公共土木施設や公共施設の復旧に迅速に取り組むとともに、自治体連携型補助金等、国の制度も活用し、都として被災した住民の生活と事業の復旧に努めること。
- 現在、末吉の全域、三根の一部で断水や水不足が続いており、トイレ、洗濯、洗い物、入浴もままならないなど、そのストレスは重大なものです。水源地からの水道管が崩落などによって断絶していることが原因であり、緊急に水源地から水を引く応急管の設置を都の負担で行うとともに、管理しやすい別ルートの検討も含めた抜本的な復旧を行うこと。
- 極めて厳しい住環境で暮らしている住民がおり、早急に安心できる住環境の提供が必要です。避難者や入居希望者に対応した住宅の提供を緊急に行うこと。
- 2019年の台風15号・19号の際に実施した一部損壊住宅への支援について、今回も実施すること。被災者生活再建支援の対象を拡大すること。
- 八丈町の農業の主力である観葉植物を栽培するパイプハウスの破壊や、レモンやアシタバのなどの農作物への壊滅的な被害に対して直接補助を行うこと。
- 漁業は水不足などにより氷が作れず、水揚げした魚の鮮度を保つことができないため、漁に出られないという事態になっています。水の補給とともに大量の水を保管できるタンクの確保など、漁業の再開に向けた支援を行うこと。
- 都が全国に誇る発酵食品くさやの業者は、台風で水冷式の乾燥機が倒壊したり、冷蔵庫が故障するなど大変な被害が生じたほか、くさや汁の維持にも困難が生じています。台風で被害を受けたそのほかの事業者も含めて、事業が継続できるよう直接支援を行うこと。
- 宿泊業者や飲食業者、レジャー事業者などはキャンセルが相次ぎ、大きな打撃を受けています。観光事業に従事する事業者にたいして、損失補填を行うこと。
- 土砂崩れによって末吉地域の教職員住宅が深刻な被害を受けました。末吉地域にとっては若い住人の存在は貴重であり、再建を求める声もあります。末吉での生活を希望する教職員がいる場合は求めに応じて、末吉地域の安全な戸建てを借り上げ教職員住宅とするなど検討すること。
- 台風によって車を失った住民がたくさんいます。住民にとって車は必要不可欠な交通手段であり、無償貸与など緊急の対応を行うこと。
- 被災した児童・生徒の学用品などの補償について、島ではコストが高くなることにより、現行の災害救助法の限度額では不足する可能性があります。島の実情に合わせて、国に増額を求めるとともに、都として上乗せ、横出しなどの支援を行うこと。
- 開館したばかりで被災し、押し流された「海・山くらし館」は貴重な地質、独自の文化を育んできた八丈島の郷土研究にとって重要な施設です。都として復旧のための支援を行うこと。
- 避難所として使った「海・山くらし館」はハザードエリアにありました。多くの地域で津波や土砂崩れの危険があり、これらの災害の危険の低い区域で用地の造成を行い、避難施設になりうる堅ろうな施設を建設するのはさまざまな困難があります。都として財政支援とともに、技術的な支援も含め、全面的に支えること。
- 復旧に必要な家屋調査や罹災証明書の発行はこれからであり、人員派遣は少なくとも年内の継続は不可避です。水道局が派遣する技術者も必要不可欠な存在であり、町の実態をよく聞き、年明け後の派遣も視野に入れ、体制を継続すること。
- 町役場の職員や八丈支庁職員、教職員は自らも被災しながら、被災住民救済のために奮闘しています。疲労も蓄積しており、適切なケアが必要です。その職責に見合った災害時の特別な手当てや休養の確保を行うこと。
- これらの支援を行なうための補正予算を編成すること。